孫子兵法序 日本語訳
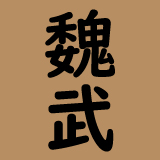
操聞上古有弧矢之利,
操(私・曹操)が聞いたところによると、太古の昔は弓矢に利があったと、
《論語》曰「足食足兵」,
論語は「食を足りさせ兵を足りさせる」(国民が食料・生活に困らず軍備も十分に)と説く、
《尚書》八政曰「師」,
尚書は八政で「師」(軍事)と説く、
《易》曰「師貞,丈人吉」,
易は「師(軍隊)の倫理が正しく、強くあれば吉」と説く、
《詩》云「王赫斯怒,爰整其旅」,黃帝、湯武咸用干戈以濟世也,
詩では「王は激しく怒り、軍隊を整えた」と言っている、黄帝、湯(殷の始祖)、武(周の始祖)も皆、干戈(武器・武力)を用いて世の中を救った、
《司馬法》曰「人故殺人,殺之可也」。
司馬法は「人が意図的(故意)に他人を殺害した場合、その人を殺しても良い(正当化される)」と説く、
用武者滅,用文者亡,夫差、偃王是也。
武(軍事的手段)に頼る者は破滅、文(平和的手段)に頼る者は亡失する例として、呉王夫差、徐の偃王がいる。(徐偃王は仁義を修めることを知りながら武を用いることを知らず、結果として国を亡くした。)
聖賢之用兵也,戢而時動,不得已而用之。
聖賢が軍を用いるのは、武器をしまっておくように(軍を控えておいて)時に応じて動かす、やむを得ない状況においてのみそれ(軍)を使う。
つまり、聖賢は正しく教育し鍛錬された軍を備えておいた上で、普段は民が充足した生活ができる平和的な政治を行い、民が安心することができない道徳倫理に外れた相手に対しては激しく怒り正義のもとに軍を動かす。
吾觀兵書戰策多矣,孫武所著深矣。
私は多くの軍事書や戦術に関する書籍を観て(読んで・研究して)きた、孫武が書いた(著した)ものは深い。
審計重舉,明畫深圖,不可相誣。
計画(計略)を見定め慎重に行動し、目標や計画は明確で長期的かつ深い洞察に基づくものであるべきで、事実でないことを広めてはならない。
而但世人未之深亮訓說,况文煩富,行於世者失其㫖要,故撰為畧解焉。
しかし世の人々はそれを深く理解せず、まして文が煩わしく富んでおり、世の(軍事を)行う者がその要点を失ってしまっているため、そこで簡略な解説を書くことにする。
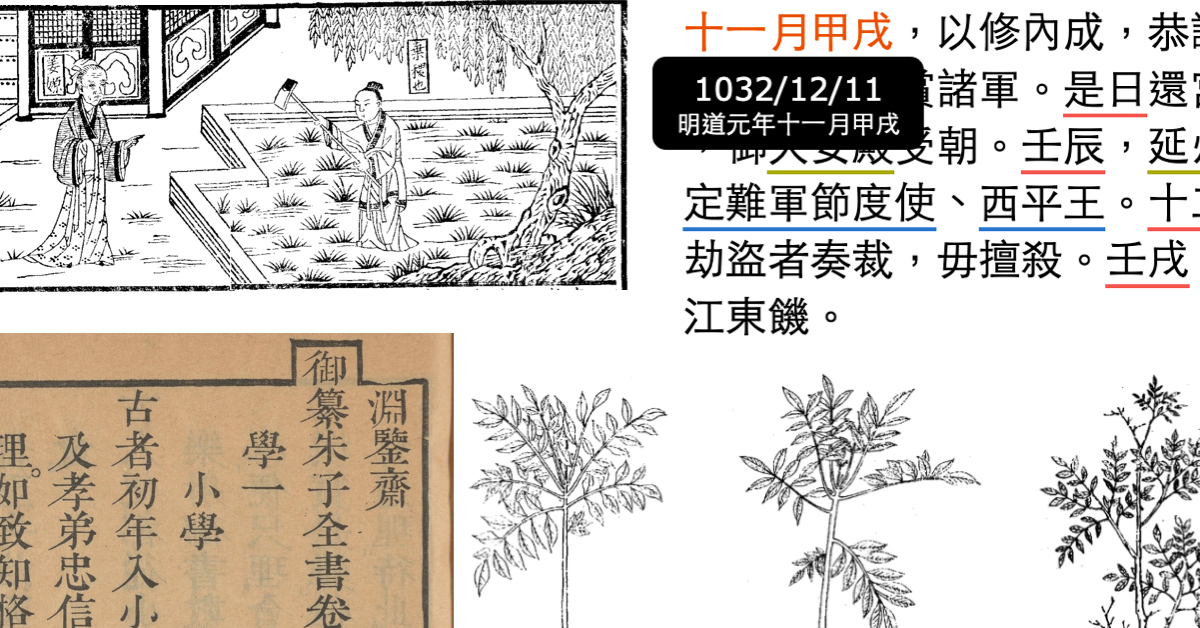
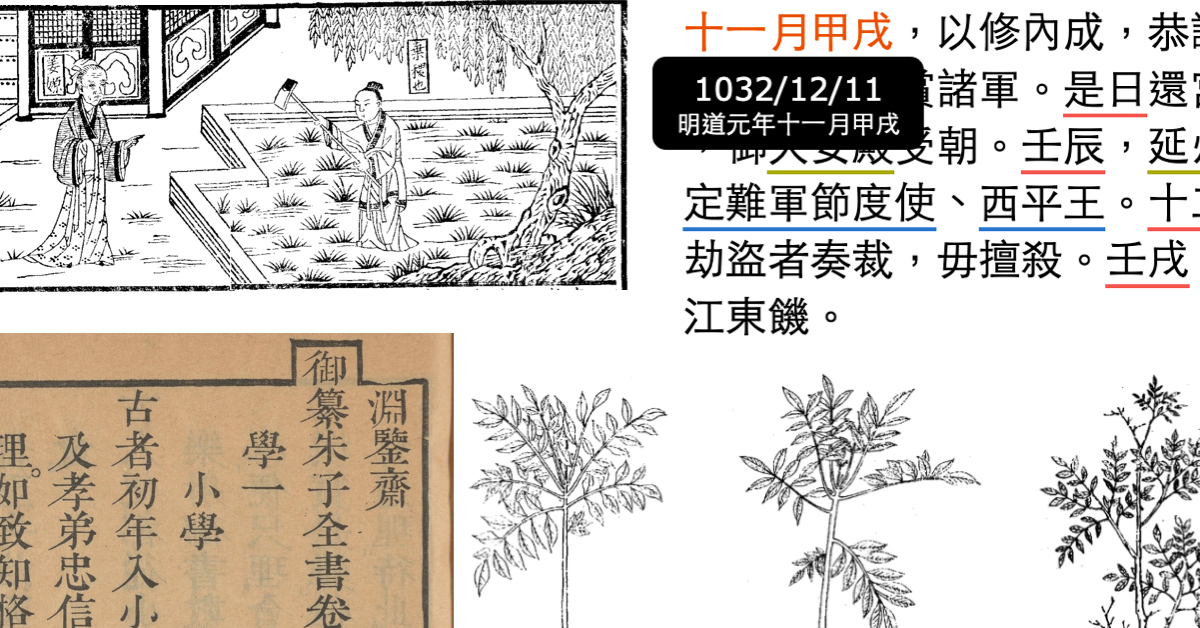
相似
操聞上古有弧矢之利,
《論語》曰「足食足兵」,
《尚書》八政曰「師」,
《易》曰「師貞,丈人吉」,
《詩》云「王赫斯怒,爰整其旅」,黃帝、湯武咸用干戈以濟世也,
《司馬法》曰「人故殺人,殺之可也」。
用武者滅,用文者亡,夫差、偃王是也。
聖賢之用兵也,戢而時動,不得已而用之。
吾觀兵書戰策多矣,孫武所著深矣。
審計重舉,明畫深圖,不可相誣。
而但世人未之深亮訓說,况文煩富,行於世者失其㫖要,故撰為畧解焉。

コメント