原文比較

独見
地者、高下、廣陜、遠近、險易、死生也
地とは、高地低地(窪地)、広い狭い、遠い近い、険しさ(険阻)易しさ(平地)、死地と生地である。
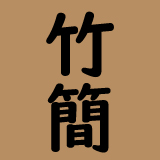
竹簡
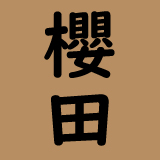
古文孫子
地者広狭遠近険易死生也
地とは、広狭、遠近、険易、生死なり
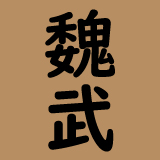
魏武注孫子

宋本十一家注
註釈
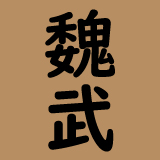
魏武注孫子
地者逺近險易廣狹死生也
曹操曰:言以九地形勢不同,因時制利也。論在《九地》篇中。
- 曹操が説く:言うところの九地とは、地形の状況が異なる(同じでない)ことを指す。時を頼りに利を制するのである。これは《九地篇》の中で論じられている。

宋本十一家注
地者逺近險易廣狹死生也
- 曹操曰:言以九地形勢不同,因時制利也。論在《九地篇》中
曹操が説く:言うところの九地とは、地形の状況が異なる(同じでない)ことを指す。時を頼りに利を制するのである。これは《九地篇》の中で論じられている。 - 李筌曰:得形勢之地,有死生之勢。
李筌が説く:形勢に適した地を得れば、生死を制する勢いがある。 - 梅堯臣曰:知形勢之利害。
梅堯臣が説く:形勢の利害を知ることである。 - 張預曰:凡用兵,貴先知地形。知逺近,則能為迂直之計;知險易,則能審步騎之利;知廣狹,則能度衆寡之用;知死生,則能識戰散之勢也。
張預が説く:だいたい軍を用いるに当たっては、まず地形を知ることが貴重である。遠近を知れば、迂直の計算ができる。険易を知れば、步騎の有利さを審らかに判断できる。広狭を知れば、兵の多少の用い方を度ることができる。死生を知れば、戦闘に勝ち残るか散り散りになるかの勢いを見極められるのである。
孫子兵法校解メモ(管理人のみ表示)
漢文叢書メモ(管理人のみ表示)
漢籍国字解全書メモ(管理人のみ表示)

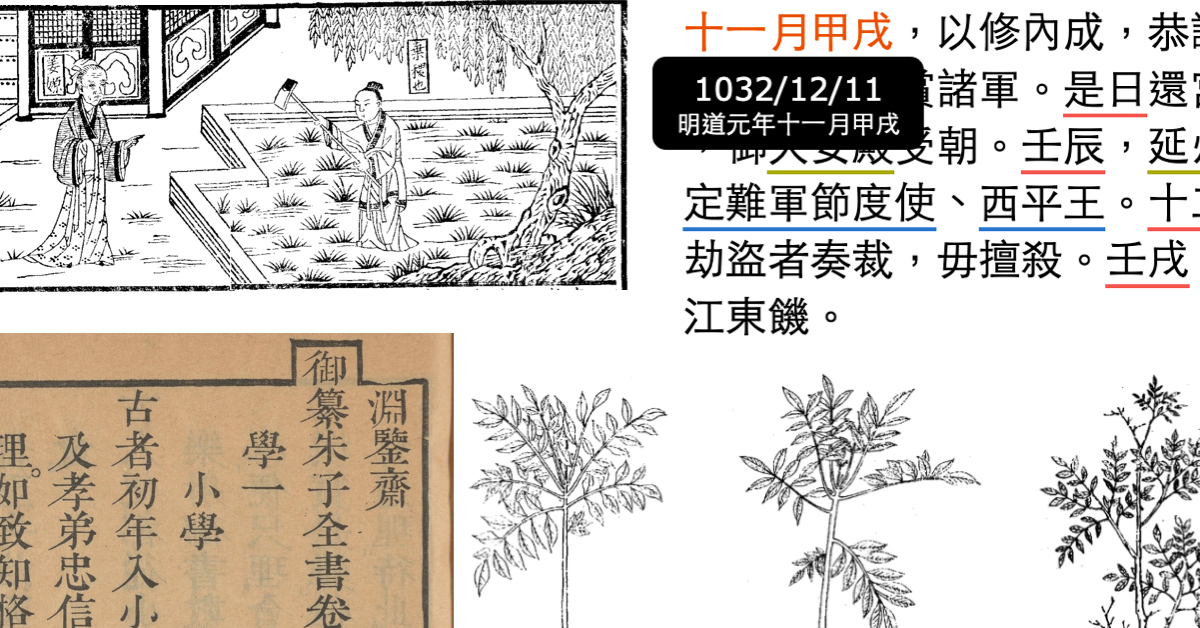
コメント