計篇(序)
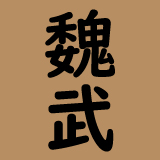
曹操曰:計者、選將、量敵、度地、料卒、遠近、險易、計于廟堂也。
曹操曰く:計者は、選將、敵を量り、地を度り、卒を料り、遠近、險易を、廟堂において計る也。
曹操が説く:戦略を立てる者は、適切な指揮官や将軍を選定し、敵の実力(軍事力や情勢)を評定し、戦場の地勢を分析して利害と弊害を割り出し、自軍の兵力を見積もり、戦場までの距離を測量し、地形の危険度を判断し、廟堂で祖先の加護を仰ぎつつ戦略を策定する。
選將(将を選ぶ):適切な指揮官や将軍を選定する。
量敵(敵情を分析する):敵の実力(軍事力や情勢)を評定する。
度地(地勢を測定する):戦場の地勢を分析して利弊(利害と弊害)を割り出す。
料卒(兵力を見積もる):自軍の兵力を見積もる。
遠近(距離を測量する):戦場までの距離を測量する。
險易(艱難か平易かを判断する):地形の危険度を判断する。
計于廟堂也(廟堂で計略を練る):廟堂で祖先の加護を仰ぎつつ戦略を策定する。

李筌曰:計者,兵之上也。《太一遁甲》先以計,神加德宮,以斷主客成敗。故孫子論兵,亦以計為篇首。
李筌曰く:計とは,兵の上也。《太一遁甲》先ず計をもって,神加德宮,以斷主客成敗。故に孫子は兵を論じ,また計をもって篇首と為す。
李筌が説く:計ることは、軍事の最上である。『太一遁甲』では、まず計り、どちらが道徳的に勝っているかにより主と客の成敗を断定する。だから孫子は軍事論では、計を最初の章に置いたのである。
杜牧曰:計,算也。曰:計算何事?曰:下之五事,所謂道、大、地、將、法也。于廟堂之上,先以彼我之五事計算優劣,然後定勝負;勝負既定,然後興師動眾。用兵之道,莫先此五事,故著為篇首耳。
杜牧曰く:計,算なり。曰く計算何事?曰く下の五事,謂うところの道、大、地、將、法なり。廟堂上において,先ずもって彼我の五事を計算し優劣す,然るのち勝負定まる;勝負既に定まれば,然るのち兵を興し眾を動かす。用兵の道,莫先この五事,故にこれを篇の首に著す。
杜牧が説く:計とは算出すること。何を算出するのか?以下の五つの事柄、いわゆる「道(道徳や指導原理)」、「天(天候や時期)」、「地(地形や位置)」、「将(指導者や統率力)」、「法(規律や戦術)」のことである。廟堂(政治や指導の中心)において、まずこれら我々と敵の五つの事柄を計算して優劣を決め、その後で勝敗を見極める。勝敗の見極めがついたら、その後で初めて軍を動かす。戦争や軍事行動を効果的に指揮し勝利を導くための戦略と原則として、これら五つの事柄よりも先に考えるべきことはなく、だからこの部分を篇の冒頭に記している。
王皙曰:計者,謂計主將、天地、法令、兵眾、士卒、賞罰也。
王皙曰く:計とは,計ることを言う主将,天地,法令,兵衆,士卒,賞罰なり。
王皙が説く:計とは、主将、天地、法令、軍事力、兵士、賞罰を計ることを言う。
張預曰く:管子曰く:“計先定于內,而後兵出境。”故用兵之道,以計為首也。或曰:兵貴臨敵製宜,曹公謂計于廟堂者,何也?曰:將之賢愚,敵之強弱,地之遠近,兵之眾寡,安得不先計之?及乎兩軍相臨,變動相應,則在于將之所裁,非可以逾度也。
張預曰く:管子曰く:“計は先ず内に定められ,しかる後兵は境を出ず。”故に用兵の道,計を以て首とする也。或る曰く:兵は敵に臨んで宜しきを制すこと貴し。曹公廟堂に於いて計を謂う者、何ぞや?曰く:将の賢愚、敵の強弱、地の遠近、兵の眾寡、安んぞこれを先ず計らざるを得んや?両軍相い臨み、変動相応ず,則ち将の裁く所に在り、度を逾えること非ざるなり。
張預が説く:管子は「計はまず内部で定められ、その後で兵が境界を越える」と。だから兵を用いる道において、計を冒頭にするのである。ある人が問う「兵は敵に対峙した際、最適な行動を取ることが重要である。なぜ曹公は廟堂での計算を重んじたのか?」と。それは「将軍の賢さや愚かさ、敵の強さや弱さ、地の位置の遠さや近さ、兵力の多さや少なさを、どうして事前に計画しないでおくことができようか?両軍が対峙し、変化に応じている状況において、その判断は将軍が行うべきものであり、危険を冒して適切な範囲を超えることは許されない。」

コメント
久しぶりに曹操の部分を加筆しました。
ですが未完成です。
また改めて加筆します。